🌧️ 日本は“雨大国”?それとも意外と“カラッと”してる?
「日本って、雨が多い国なんだろうか?少ない国なんだろうか?」
そんな疑問を持ったことはありますか?
そして、あなたが住んでいる地域の1年間の降水量って、どれくらいか知っていますか?


💧 雨の単位「mm」って実はよく分からない問題!
雨の量は「ミリメートル(mm)」で表します。
…でも正直、普段の生活で「mm」で雨を考えることって、あまりないですよね。
「100mmって多いの?少ないの?」ってピンとこない人も多いはず。
📏 東京の年間1500mm=150cmって…どんだけ降ってるの!?
東京では、1年間におよそ1500mmの雨が降ります。
これをわかりやすくすると…150cm!
つまり、東京のある場所に容器を置いて1年間放置したら、身長150cmくらいの人の背丈まで水がたまるイメージ。
ちょっと驚きませんか?
ちなみに世界の平均は約880mm。
東京は世界平均のほぼ2倍の雨が降っていることになります。
☔ 雨の正体は「空気が○○する」たったひとつのシンプルな理由
「なんで雨が降る地域と降らない地域があるんだろう?」
これを理解するためには、まず雨の仕組みから。
すごくシンプルに言うと…
1️⃣ 地表の湿った空気が上昇する(=上昇気流)
2️⃣ 上空で冷やされて雲ができる
3️⃣ 雨になる!
前回の「気温」の記事を読んでくれた人は覚えているかも。
上空にいくほど気温が下がる → 水蒸気が水滴に変わる → 雲ができる、という流れです。
ここで出てくるキーワードが「気圧」。
高気圧は空気を押し下げる(下降気流)、低気圧は空気が上に上がる(上昇気流)。
だから、低気圧の日は雨、高気圧の日は晴れになりやすいんです。
🌍 地球全体で見ると“雨の多い帯”と“少ない帯”があった!
実は地球規模で見ると、「雨が多いエリア」「少ないエリア」があるんです。
- 🌴 赤道付近(0〜20°):低気圧=雨が多い
- 🏜️ 中緯度(20〜40°):高気圧=雨が少ない
- 🌧️ 高緯度(40〜60°):低気圧=雨が多い
- ❄️ 極地(60〜90°):高気圧=雨が少ない(雪が舞ってるけど実は“降水量”は少ない!)
この「大気の帯」を知っていると、地図を見ただけでその国の降水量がなんとなく予想できちゃいます。
🌪️ 雨を生み出す4つのパターンがある!
上昇気流が起きると雨が降りやすいのですが、そのパターンは大きく4つ!
1️⃣ 地形性降雨:山に風がぶつかる
2️⃣ 対流性降雨:地面が温められて空気が上がる
3️⃣ 前線性降雨:暖かい空気と冷たい空気がぶつかる
4️⃣ 収束性降雨:低気圧で空気が集まる
🗾 日本海側・熱帯スコール・梅雨…世界の“雨パターン”を大解剖!
- 日本の冬の日本海側:シベリアからの季節風+山での地形性降雨で雪や雨が多い
- 熱帯のスコール:日中の熱で空気が急上昇→夕立や土砂降りに
- 日本の梅雨:暖気と寒気がぶつかって前線性降雨
- インド・チェラプンジ:ヒマラヤに湿った風がぶつかって雨が降る。(なんと年間26000mm超で世界記録を持っています!)
🌱 雨=迷惑?…実は暮らしと命を支える“超重要)キャラ”だった!
「雨って正直、通勤・通学やレジャーの敵…」と思われがちですが、
実は農業や人が住む場所を決めるうえで超重要な要素。
だから、降水量を知ることは「暮らしの地理」を理解する第一歩なんです。
次回は「なぜ風が吹くのか?」について。お楽しみに!
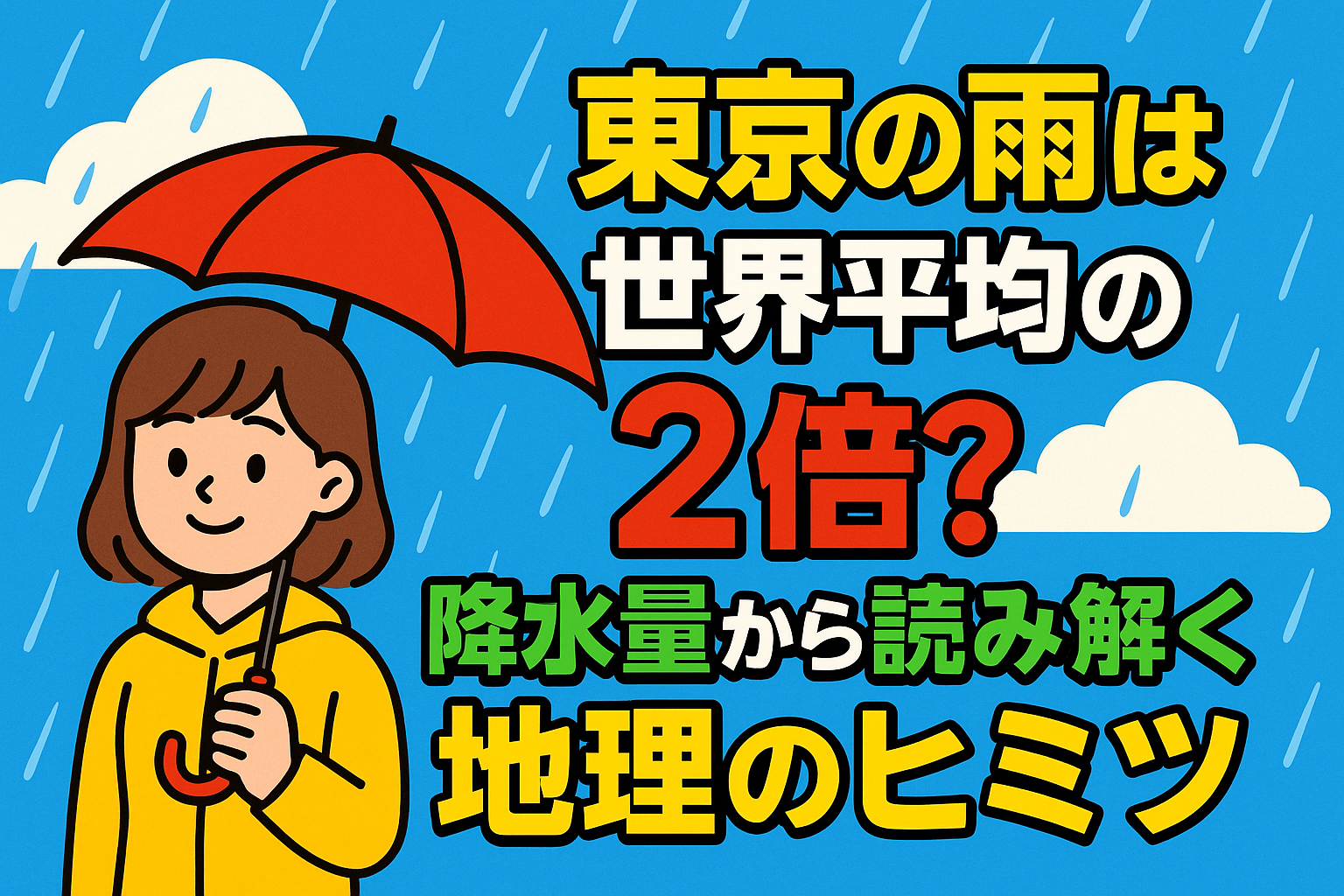


コメント