✅ 混沌の中に、学びの光を探しに行く―バングラデシュへ
世界一周の旅、2か国目はバングラデシュを計画しています。
急速に発展し続けるメガシティ「ダッカ」を中心に、地理教師として
「都市化」・「交通」・「開発」のリアルな現場を体感したいと思っています。
バングラデシュは、地理の教科書では「南アジアの農業国」として紹介されることが多い一方で、
ここ数年で、世界でも最も急速に都市化・経済成長を遂げている国の一つでもあります。
都市の成長、人口の集中、インフラの課題、交通の混沌……
こうした現代都市が抱えるリアルな問題を、自分の目で見てみたい!
そんな想いで、バングラデシュを訪れます。
📚 バングラデシュの基本情報(予習データ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 首都 | ダッカ(Dhaka) |
| 人口 | 約1億7,000万人(世界第8位) |
| 公用語 | ベンガル語 |
| 通貨 | タカ(BDT) |
| 時差 | 日本より−3時間 |
| 気候 | 熱帯モンスーン気候(Aw) |
🌍 ポイント:
- ダッカ首都圏の人口は約2,200万人(東京圏に匹敵)
- 急激な人口増加とインフラ整備の遅れが交通混雑を引き起こしている
- ガンジス川水系の豊かな水資源があるが、都市排水との両立が課題
🚧 体験したいこと①:メガシティ・ダッカを歩く
首都ダッカは、世界で最も人口密度の高い都市の一つ。
街に一歩出れば、クラクションの嵐。
渋滞・バイク・リキシャ・歩行者が入り乱れる「混沌」の世界が広がっているとも言われています。
このような「都市の混雑と、そこに生きる人々の生活」という視点で歩いてみたいと思います。
- 都市化のスピードと計画的開発のギャップ
- 公共交通の整備状況と、リキシャ・三輪タクシーへの依存
- スラムと高層ビルが混在する都市構造
教科書だけでは伝えきれない、急速に変わり続ける都市の姿を体感してみたいと思っています。

🚤 体験したいこと②:水上交通のある暮らし
ダッカやその周辺の都市では、ガンジス川水系(ブラマプトラ川)の豊富な水路を活かして、
フェリーやボートといった水上交通が今も重要な役割を果たしています。
- 毎日数万人が利用する大きな船着き場「スダーバン・ローンチターミナル」
- バングラデシュ南部では、川が道路代わりに使われている地域もあるとのこと
同時に、気候変動や洪水リスクのある地域での交通インフラとしての課題も感じたいと思っています。
💡 地理教師の注目ポイント|イスラム・ジュート・歴史の三本立て!
バングラデシュを見てみたい理由は、実は「都市」や「交通」だけじゃないんです。
この国を語るときに面白いのは――宗教・産業・歴史、まさに三本立て!
🕌 ① 南アジアのイスラム教ってどんな感じ?
バングラデシュは国民の約9割がイスラム教徒。
でも、同じイスラムでも、西アジアのアラブ世界とはちょっと雰囲気が違うとも言われています。
例えば、インドのヒンドゥー文化との交流や、インドネシアのイスラムとの比較をしてみると、
「同じイスラムでも土地によってこんなに違うんだ!」というのが見えてくるはず。
宗教の地理って、教科書の一文だけじゃイメージしづらいから、現地で肌で感じたいテーマのひとつです。
🌱 ② 世界を席巻する“ジュート王国”
「ジュート」って知ってますか?
麻の一種で、環境にやさしい素材としてエコバッグやカーペットに使われています。
実はその約9割以上を、インドとバングラデシュの2か国で生産しているんです!
他の国ではほとんど作られていないから、まさに「ここにしかない地理教材」
現地の畑や工場を見られたら、「持続可能な資源と産業」の生きた例として授業に持ち帰りたいなと思っています。
🌏 ③ お隣の国との関係って?
バングラデシュは1971年にパキスタンから独立した国。
インドとの関係も、仲良しだったり、政治的には複雑だったり…。
「お隣の国をどう思っているのか?」っていう素朴な質問を、現地の人に投げかけてみたいです。
国同士の歴史や政治はニュースで学べるけど、暮らす人々の実感は現地でしか聞けません。
こうしたテーマを組み合わせると、
- 「宗教の多様性」
- 「持続可能な産業」
- 「歴史と国際関係」
という、バングラデシュのさまざまな顔が浮かんできます。
授業では「バングラデシュをどう捉えるか?」を問いかけられるような、そんな教材にしていきたいです!
🎒 出前授業の構想(もし学校訪問できたら)
- 日本の交通事情を紹介し、比較する授業
- けん玉や将棋体験を通じた文化交流
- 「川のある暮らし」をテーマにした意見交換
英語やジェスチャーを交えて、現地の子どもたちと“交通と暮らし”の違いを語り合う時間を持てたら最高です。
2024年4月、私は教員対象青年海外協力隊(バングラデシュ)に応募しました。バングラデシュの子どもたちに、将棋を教えてみたいと考えていましたが、残念ながら2次試験で不合格となってしまいました。
それ以来、今度は自分で必ず行って実現させてみようと考えてきたので、2か国目はバングラデシュを選びました。
JICA不合格だったときの記事はこちら。

📝 おわりに|混沌の中に、人々のたくましさを見る旅へ
バングラデシュというと、日本ではあまり馴染みがないかもしれません。
でも、ここには「世界が向かう未来の都市像」があるように感じます。
不便さや課題の中に、たくましく生きる人たちの暮らしがある――
そのリアルな姿を、五感で感じて、次の授業に生かしていきたいと思います。
次回は、インド編。
ガンジス川の沐浴と、宗教都市・ヴァラナシの予習へと続きます!



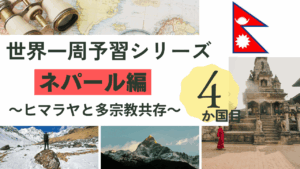
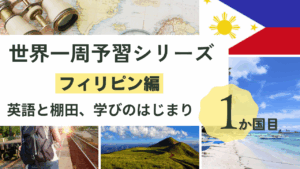
コメント