✅ 20年越しの再訪から始まる、インドでの学び
世界一周の旅、3か国目はインド。
この国は、文化・宗教・人の多様性に満ちあふれた“文明の十字路”です。
地理の授業でも、ヒンドゥー教・仏教・イスラム教などの宗教地理や、人口、農業、IT産業まで幅広く登場するインド。今回の訪問では、「宗教と水資源」「都市と自然の共存」というテーマで、現地のリアルな暮らしと信仰の風景を体感したいと思っています。
📚 インドの基本情報(予習データ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 首都 | ニューデリー |
| 人口 | 約14億人(世界最多) |
| 公用語 | ヒンディー語・英語 他22言語 |
| 通貨 | インド・ルピー(INR) |
| 時差 | 日本より−3.5時間 |
| 気候 | 熱帯モンスーン(Aw)〜ステップ気候(BS)まで多様 |
🌍 ポイント:
- 多言語・多宗教国家。憲法上の「世俗主義」を掲げる
- 川=神聖な存在とされ、特にガンジス川は“女神”とされている
- 気候帯の多様性により農業・生活スタイルも変化に富む
🛕 体験したいこと①:ガンジス川のほとりで信仰と暮らしを感じる
訪れる予定地は、北インドの聖地ヴァラナシ。
ここはヒンドゥー教最大の巡礼地であり、「死ぬ前に一度は訪れたい聖地」とされる場所です。
- 沐浴する人々と祭礼の光景
- 川辺に建つ寺院群と火葬場(特にマニカルニカー・ガート)
- 水資源としてのガンジス川の役割と課題(水質・信仰の両立)
ただの河川ではなく、“生きている存在”としての川を、人々がどう扱い、祈り、暮らしているのか――それを見に行きます。


🌾 体験したいこと②:インドの農村と都市を比較する
可能であれば、農村エリアにも足を運びたいと考えています。
- モンスーン気候下の水田と農業風景
- 農業と宗教行事のつながり(収穫祭など)
- 地方と都市の経済格差や生活インフラの差
また、都市部(デリーやコルカタなど)と農村との「発展の段差」も注目点。
交通手段、商業施設、教育格差、識字率など、地理的な視点でインドの地域間格差を感じたいです。
🕰️ 20年前の自分と再会する旅へ
実は私がインドを訪れるのは、これがはじめてではありません。
大学生の頃、バックパッカーとしてひとり旅でインドを歩いた経験があり、当時の記録も残っています。
【関連記事(Note)】


その中でも特に印象に残っているのが、今回再訪予定のヴァラナシ。
あのとき、ガンジス川の朝焼けを見て感じた「言葉にできない何か」は、20年経った今でも心に残っています。
だからこそ、今回はもう一度この地に立ち、あの頃の自分と今の自分を重ねてみたい。
変わったもの、変わらないもの。
20年の時を超えて、地理教師という立場からこの地を見たときに、どんな感情が湧いてくるのか、とても楽しみにしています。
「ガンジス川は変わらない。でも、自分は変わった。」
そんな発見をしたいのです。
🎒 出前授業と、祈りの街コルカタへふたたび
今回のインド訪問では、もし可能であれば、再び現地の子どもたちや学校と交流する機会を持ちたいと思っています。その中でも私にとって特別な場所が、コルカタにあるマザーテレサの「マザーハウス」です。
🕊️ 20年前のボランティア体験と再訪の願い
大学生の頃、インドを一人旅していたときに、マザーハウスで数日間のボランティア活動をさせていただいたことがあります。そこでは、ホームレスの方や障がいのある方、孤児たちとふれあいながら、言葉では言い表せない「祈りと奉仕」の空間に触れました。
「世界には、言葉を超えて分かち合えるものがある」
そう感じた瞬間でもありました。
今回の世界一周で、もう一度この場所を訪れたい。
あのときとは違う視点――教師として、父親として――でこの場所を見つめ直したとき、何を感じるのかを確かめてみたいです。
🧑🏫 出前授業で伝えたいこと
- 「日本とインドの暮らしや価値観の違い」
- 「水や宗教とともに生きる文化」
- 「けん玉や将棋を通じた交流」
などを、英語や身振り手振りで届けたいです。
同時に、子どもたちからも「あなたの暮らし」「あなたの学校」「あなたの祈り」を教えてもらえたら嬉しいです。
マザーハウスという、人間の尊厳を見つめる場を再訪する流れの中で、子どもたちと対話する時間が生まれたら――それは、まさにこの旅の原点につながる瞬間になる気がしています。
📝 おわりに|川とともに生きる人々を見に行く
インドは、一言で語り尽くせないほどの多様性を抱えた国。
でもその中で私が特に興味を持っているのは、「自然を敬う暮らし」が今も生きていることです。
ガンジス川を見て、「ああこれが教科書に載っていた場所か」と終わらせるのではなく、人々の祈りと文化の蓄積を体感する旅にしたいです。
次回4カ国目はネパールへGO!!
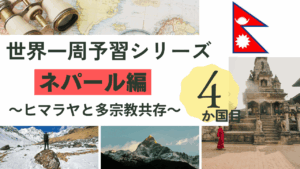



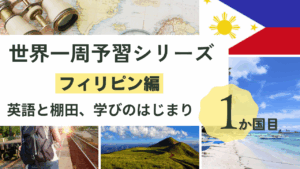
コメント