🏔️ ヒマラヤの麓で「人と自然と信仰の共存」を見に行く
世界一周の旅、4か国目はネパール。
この国には、世界最高峰エベレストを含むヒマラヤ山脈と、多様な宗教・民族が共存する社会があります。
でも、ネパールの魅力はそれだけではありません。
訪れた人が口々に言うのは、「ネパールに行くとほっとする」「心が癒される」という声。
私自身、これまで多くの生徒や旅人からその話を聞いてきました。
ヒマラヤのようにおおらかで、素朴で優しい人々。
ごちゃごちゃした喧騒から離れ、山と空と人の笑顔に囲まれた土地。
そんなネパールで、地理教師としての視点と、一人の旅人としての心を両方開いて、いろいろなものを感じてきたいと思っています。
📚 ネパールの基本情報(予習データ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 首都 | カトマンズ |
| 人口 | 約3,000万人 |
| 公用語 | ネパール語(他にも多数の少数言語) |
| 通貨 | ネパール・ルピー(NPR) |
| 時差 | 日本より−3時間15分 |
| 気候 | 高地:寒冷、高原〜低地:温暖・モンスーン型(Aw〜H) |
🌍 ポイント:
- ヒンドゥー教約80%、仏教約10%、イスラム教約4%
- ヒマラヤ山脈は、インド=オーストラリアプレートがユーラシアプレートに衝突することで誕生
- 貝の化石が見つかるなど、かつて海だった名残が山中に残る
- 「狭まる境界」なのに火山が少ないといった特徴も、地理的に興味深い
こうした話は、私の授業でも扱っていて、「なぜヒマラヤに貝の化石?」「なんで火山がないの?」という問いに、生徒たちは興味を持って話を聞いてくれます。
だからこそ今回は、それらの地形のリアルな現場をこの目で見てきたいのです。
🏞️ 体験したいこと①:ヒマラヤ山麓の「標高と暮らし」
今回は、ポカラ周辺の山岳地帯を訪れ、
- 標高による植生・気候・家屋構造の違い
- 棚田の水利の工夫と地形適応の技術
- 山岳トレッキング文化と観光の共存
など、自然と共に生きる知恵を学びたいと思っています。
それは教科書に書かれている「高地の農業」や「地形と気候」の話が、リアルな教材として再定義される瞬間になるはずです。
🕌 体験したいこと②:多宗教の共存と寛容さを感じる
ネパールでは、ヒンドゥー教と仏教の祈りの場が同じ空間に存在していることが多くあります。
- 「スワヤンブナート」では、仏教ストゥーパにヒンドゥー教徒も祈る
- 「パシュパティナート」では、火葬場を見守る静けさの中に宗教の境界が消える
宗教と地理が重なる瞬間――それを見に行きたいのです。
🧑🏫 地理教師としての視点とねらい
- プレート境界で生まれた山脈の“その後”を観察
- 火山はなぜない?という生徒の疑問にリアルで答える
- 地形と気候と人の暮らしが結びつく場所を教材に変える
- 宗教と共存する空間デザインを地理+公民的視点で読み解く
🎒 出前授業の構想|ヒマラヤの子どもたちと交流する
もし現地の学校に訪問できれば:
- 「富士山とエベレスト」比較クイズ
- 「海があった山で貝が見つかる?」地質のお話
- けん玉や将棋で、集中力の文化を紹介
- 「四季のある国・日本の暮らし」を共有
→ どれも、あなたの国って面白いね!をお互いに言える授業にしたいです。
📝 おわりに|地層だけじゃない、「人のやさしさ」にも出会いたい
プレートが押し合ってできた巨大な山脈。
その地層の中に眠るかつての海の記憶。
地形と宗教が折り重なる風景。
ネパールという国には、教科書を超えたリアルな「地理の物語」が広がっています。
そしてもう一つ
この国を訪れた人が「ほっとする」と語る理由も、ぜひ自分の体で感じてみたい。
それは、きっとヒマラヤだけじゃなく、そこに暮らす人々の笑顔や心のあたたかさがあるから。
🏔️ ネパールの“高い場所”で見えるのは、絶景だけじゃない。
そこには、人と自然と文化が溶け合ったやさしい地理がある。
🔜 次回予告:チベット編へ
次回は、チベット自治区。
酸素の薄い高地と、チベット仏教の世界を体感する旅へ続きます。




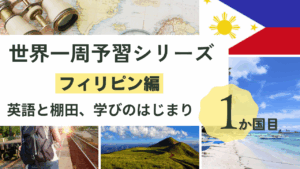
コメント